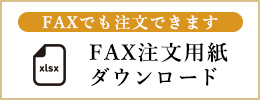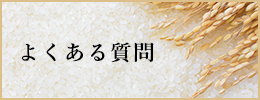日本三大そば(長野・戸隠、島根・出雲、岩手・わんこ)と日本三大うどん(香川・讃岐、秋田・稲庭、長崎・五島)が全て揃った乾麺の詰め合わせセットです。
それぞれの味、食感、コシといった違いを楽しみながら食べ比べて頂ければと思います。
常温で長期保存ができますので、非常食としてもご活用頂けます。
※めんつゆは付属しておりません。
※三大そば、三大うどんの選定方法や由来については諸説ありますが、本詰合せセットでは下記の通りとしておりますので、ご了承の程、よろしくお願い致します。
【戸隠そば】古くから山岳信仰の聖地とされた長野市の戸隠山を訪れる修行僧が携帯食として蕎麦粉を持ち、水にといて食べていました。江戸時代に入ると「そば切り」の技術が伝わり、修行者へのおもてなしとして、そばが振る舞われるようになりました。
【出雲そば】3代将軍徳川家光の頃、信濃松本藩主松平直政が出雲松江藩に国替えを命じられた際、松本からそば職人を一緒に松江に連れてきたことにより、この地にそばが伝わったとされています。粉の選別をせず、玄そば(殻のついたそばの実)をそのまま挽き込む「挽きぐるみ」と呼ばれる製法の為、他のそばよりも黒っぽく見えるのが特徴です。
【わんこそば】発祥の地とされる盛岡市、花巻市では客人をそばでもてなす習慣があり、客人が多くても熱々のそばを食べてもらえるよう少量ずつ配ったのが始まりとされています。また、江戸時代初期に盛岡藩主南部利直に献上した際に、利直が気に入って何度もお代わりをしたのが始まりという説もあります。
【讃岐うどん】平安時代初期、讃岐国出身で遣唐使一行の留学僧であった弘法大師空海が唐から伝えたという言い伝えがあります。讃岐国は江戸時代には全国的にも知られた上質の小麦の産地となっており、小豆島では塩や醤油の製造が盛んでもあったこともあり、うどん作りも盛んに行われていたようです。
【稲庭うどん】江戸時代初期に今の秋田県湯沢市稲庭地区の佐藤市兵衛が干しうどんを製造したことが始まりとされています。その後、秋田藩主佐竹氏の「御用」となり、参勤交代の際の幕府への献上品にもなりました。明治になると明治天皇にも献上されるなど、一般市民がなかなか口にする機会が無かったのですが、1972(昭和47)年にようやく佐藤家が秘伝としてきた製造方法が公開されると、一般に広く知られるようになりました。
【五島手延うどん】奈良時代から平安時代初期、五島列島は遣唐使の寄港地であり、遣唐使から伝えられたとされています。麺生地を伸ばしていく過程で、麺同士がくっつかないように五島列島特産の食用椿油を生地に練り込むことが特徴です。五島列島の海流で育った飛魚(あご)のだしから作られるつゆとの相性が抜群です。(※つゆは付属しておりません)
※大変申し訳ございませんが、沖縄・離島へのお届けは「送料込」対象外地域となります。別途差額運賃と中継料等が発生致します。ご注文確認後、当方よりご連絡させて頂きます。予めご了承願います。
◆簡易包装・資源節約の観点から、のし・ラッピング等は対応しておりません。ご了承願います。
※予告なく商品パッケージ・ラベル等変更する場合がございます。ご了承願います。
| 原材料 | 【戸隠そば】そば粉(そば(長野県産))、小麦粉、そばの葉粉末 【出雲そば】小麦粉(小麦(国産))、そば粉(そば(国産))、食塩 【わんこそば】小麦粉(小麦(国産))、そば粉(そば(国産))、食塩 【讃岐うどん】小麦粉(小麦(香川県産))、食塩 【稲庭うどん】小麦粉(国内製造)、食塩、でんぷん 【五島手延うどん】小麦粉(国内生産)、食塩、なたね油、大豆油、椿油(一部に小麦・大豆を含む) |
|---|---|
| 内容量 | 【戸隠そば】340g(約4人前)×3袋 【出雲そば】180g(約2人前)×1袋 【わんこそば】240g(約3人前)×2袋 【讃岐うどん】300g(約3人前)×3袋 【稲庭うどん】180g(約2人前)×1袋 【五島手延うどん】300g(約3人前)×1袋 |
| 賞味期限 | 【戸隠そば】480日 【出雲そば】730日 【わんこそば】360日 【讃岐うどん】365日 【稲庭うどん】730日 【五島手延うどん】365日 |
| 保存方法 | 常温保存(直射日光や高温多湿を避ける) |
| 配送形態 | 佐川急便 |
| 特定原材料 (8大アレルゲン) |
卵:× 乳:× 小麦:○ そば:○ 落花生:× えび:× かに:× くるみ:× |
| 製造者・販売元 | (製造者) 【戸隠そば】株式会社おびなた 【出雲そば】有限会社本田商店 【わんこそば】株式会社小山製麺 【讃岐うどん】株式会社讃岐物産 【稲庭うどん】株式会社稲庭吟祥堂本舗 【五島手延うどん】五島手延うどん協同組合 |
送料込